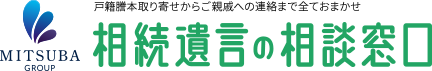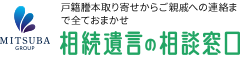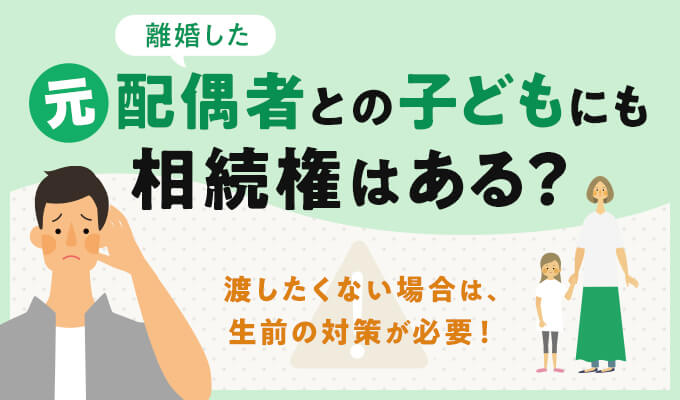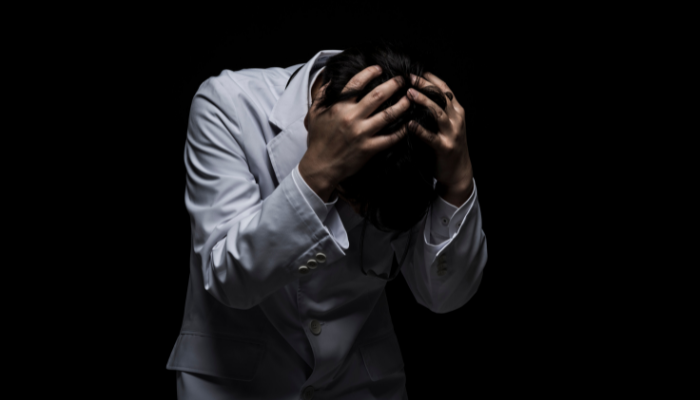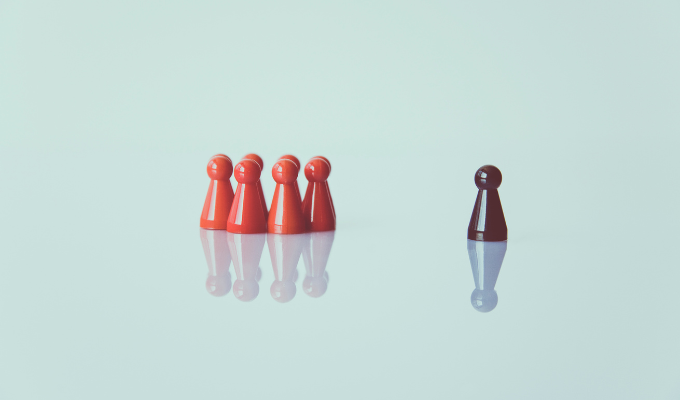相続税
遺族年金はいつまで受け取れる?手続き期間や受給額の具体例も

家計を支えていた方が突然亡くなった場合、生活が苦しくなる家庭もあるでしょう。そんな遺族の生活を助ける「遺族年金」という制度があります。遺族としては可能な限り受給し続けたいものですが、いつまで受け取り続けられるのでしょうか。
この記事では遺族年金の受給期間と手続きする期限、受給額を紹介します。遺族年金について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
遺族年金はいつまでもらえる?
遺族年金はいつからいつまで受け取れるのでしょうか。そもそも遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類あります。
違いは次の通りです。
| 項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 支払っている年金の種類 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 加入者 | 国民全員 | 会社員・公務員 |
| 受給できる人 | 18歳未満の子どもがいる配偶者 18歳未満の子ども |
優先順位が高い順 1配偶者または子ども 2両親 3孫 4祖父母 (優先順位が高い順に) |
国民年金の加入者が亡くなった場合、遺族基礎年金が支給されます。ただし18歳未満の子どもがいることが条件です。
一方、会社員や公務員が加入しているのが、厚生年金です。厚生年金の支払者が亡くなった場合、遺族厚生年金が支給されます。
優先順位の高い人から受給できるため、基本的には配偶者や子どもが受け取ることになります。
遺族基礎年金は子どもが18歳になるまで
遺族基礎年金は子ども18歳になるまで受給できます。18歳になると年金は打ち切られます。また子どもが複数名いる場合は、18歳未満の子だけが受給対象です。
例えば19歳を筆頭に3人の子どもがいる想定だと、下記の通りとなります。
| 項目 | 年齢 | 受給対象者 |
|---|---|---|
| 長男 | 19歳 | × |
| 次男 | 16歳 | 〇 |
| 三男 | 14歳 | 〇 |
長男の分は受け取ることができませんが、次男、三男の遺族基礎年金は受け取れます。しかし三男が18歳になると、遺族基礎年金は全員分受け取れなくなります。
ただし障害者等級1級または2級の子どもは20歳まで受給できます。
遺族厚生年金は原則、期限はない
遺族厚生年金は原則、生涯受け取ることが可能です。ただし子どもがいる30歳以上の配偶者のみです。
30歳未満の配偶者であれば、支払っていた方が亡くなった翌月から5年間しか受け取れないため注意してください。また配偶者が新しい人と結婚した場合や、子どもが養子縁組の場合などは受給対象者から外れます。
【関連記事】相続した不動産を売却して相続税を支払う方法|申告前の計算と節税対策
遺族年金の手続きはいつまでに行えばよいのか

では遺族年金を受給するためには、いつまでに手続きをすればよいのでしょうか。ここでは手続き期限と受給開始までの期間、手続きの流れについて解説します。
亡くなった日の翌日から5年以内
遺族年金の手続きは、支払っていた方が亡くなってから5年以内と定められており、期限が過ぎると時効が成立して受給できなくなります。5年というと長い気もしますが、遺族年金のことを忘れてしまわないように、すぐに手続きを済ませておきましょう。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の必要書類と請求先はこちらの表を参考にしてください。
| 項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 提出先 | 市区町村役場の窓口 | 各都道府県の年金事務所 年金相談センター |
| 請求書 | 国民年金請求書 国民年金請求書(別紙) |
厚生年金請求書 厚生年金請求書(別紙) |
| 必要書類 | 年金手帳 戸籍謄本 世帯全員の住民票の写し 死亡者の住民票の除票 請求者の収入が確認できる書類 子どもの学生証 死亡診断書のコピー 受取先金融機関の通帳等 認印 |
手続き開始から支給開始までは約4カ月
遺族年金の手続き開始から支給開始までは約4カ月かかります。主な流れは下記の通りです。
- 受給資格を取得して年金請求を行う
- 年金証書・年金決定通知書が送付される
- 年金振込通知書・年金支払い通知書が送付される
- 初回受給
必要書類の準備なども考慮すると、手続き開始から初回受取まで4カ月弱かかります。受取後は偶数月の15日に支払われます。
<受給日>
- 2月15日
- 4月15日
- 6月15日
- 8月15日
- 10月15日
- 12月15日
ただし過去にさかのぼって遺族年金の受給を行う場合、奇数月に支払われる場合もあるため、手続き先に確認しておきましょう。
【関連記事】遺産相続で成年後見人が必要なケースは?選ぶ流れや費用、注意点を解説
相続や遺言の
無料相談受付中!
-
電話での無料相談はこちら
0120-243-032
受付時間 9:00~18:00
(土日祝日の相談は要予約) -
メールでの
無料相談はこちら

遺族年金を受け取れる金額と期間の目安

それぞれの遺族年金を受給する場合の目安を見てみましょう。
遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金は基本額(777,800円)に加算額を加えた金額を1年間で受け取ることが可能です。加算額は子どもの数に応じて下記の通りに定められています。
- 第一子:223,800円
- 第二子:223,800円
- 第三子以降:74,600円
子どもの数が多いほど、受け取れる遺族基礎年金の支給額は大きくなります。下記の表は子どもの数に合わせた目安表です。参考にしてください。
| 子どもの数 | 合計受給額 |
|---|---|
| 1人 | 1,001,600円 |
| 2人 | 1,225,400円 |
| 3人 | 1,300,000円 |
| 4人 | 1,374,600円 |
| 5人 | 1,449,200円 |
なお、配偶者がおらず、子どもだけの場合、第一子分の加算額を差し引いた金額が合計受給額となります。
例えば子ども2人だけの場合、1,001,600円(777,800円+223,800円)、子ども3人だけの場合は、1,076,200円(777,800円+223,800円+74,600円)となります。
遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金の受給額は下記の計算式のうちいずれか大きいほうの金額となります。
- (平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数)×3/4
- (平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年3月以前の被保険者期間+平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間)✕3/4
さらに年齢に合わせて加算される金額もあります。
| 項目 | 中高齢寡婦加算 | 経過的寡婦加算 |
|---|---|---|
| 加入者の条件 | 40歳~65歳までに亡くなった | 65歳以降に亡くなった |
| 加算額 | 583,400円 | 年金給付の経過措置一覧(令和 4 年度)にて確認 |
中高齢寡婦加算は遺族厚生年金の受給額が583,400円加算される制度です。該当する方は下記のいずれかに当てはまる方です。
- 亡くなった時の年齢が40歳以上65歳未満であり、生計を同じくしている18歳未満の子がいない配偶者である
- 子が18歳になり遺族厚生年金が受け取ることができない
経過的寡婦加算は65歳から亡くなるまで遺族厚生年金に加算される金額のことです。受給できる方は下記のいずれかに該当している必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給を開始した
- 中高齢寡婦加算を受け取っていた妻が65歳になった
要件を満たせば自分の年金も受け取れる
原則、1人が受給できる年金は、1種類だけとされています。しかし要件を満たせば遺族年金と自分の年金である老齢年金の両方を受け取ることが可能です。
要件は下記の2種類のいずれかを満たしている必要があります。
- 自分の年金が老齢基礎年金だけの場合
自分の年金が老齢基礎年金でかつ、遺族厚生年金受給の要件を満たしている方は、両方受け取れます。
- 遺族厚生年金の金額より老齢厚生年金のほうが低い場合
自分の老齢厚生年金が、遺族厚生年金の金額より低い場合、その差額分が受け取れます。
しかし遺族基礎年金と老齢年金は、両方受け取ることができません。どちらか金額の高いほうを選ぶようにしてください。
特別支給の老齢厚生年金との併用はできない
特別支給の老齢厚生年金とは、男性は昭和36年4月1日以前に、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人が受給できる年金です。また老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があることや厚生年金保険などに1年以上加入していたことなども条件です。
過去には年金制度の改定が多くあったことから、利益を平等にするために設けられた特別措置です。遺族厚生年金と両方受け取ることはできないためどちらか金額の大きいほうを選ぶようにしましょう。
まとめ
今回は、遺族年金の受給期間や、手続きの期限、受給額を紹介しました。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、支払っていた年金の種類によって、受け取れる期間や受給者、金額が異なります。
遺族基礎年金は基本額と加算額分が受け取れますが、子どもの年齢が大きなポイントです。18歳を過ぎると受給できなくなるため注意してください。
カテゴリ